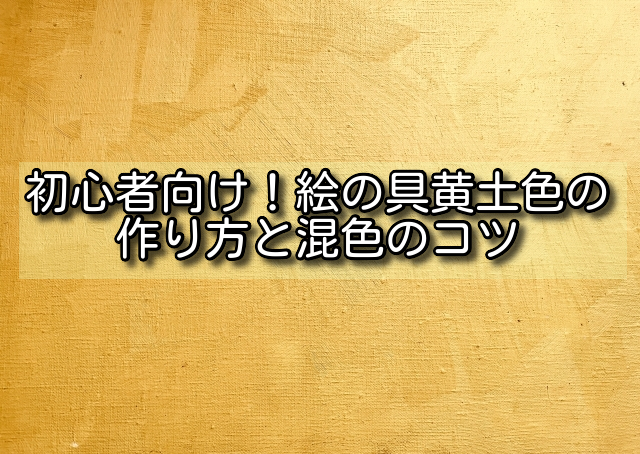絵の具の黄土色は、自然や落ち着きのある風景を描く際に欠かせない色のひとつです。しかし、既製品だけに頼らず、自分で黄土色を作れるようになると、表現の幅はぐんと広がります。
絵の具の黄土色の作り方には、どんなコツがあるのでしょうか?
本記事では、三原色を使った基本的な絵の具の黄土色の作り方から、アクリル・水彩・ポスターカラーといった絵の具別のコツ、さらには色鉛筆やクーピーでの表現法まで、詳しくご紹介します。
ダイソーやセリアなど100均で揃えられる材料も取り上げるので、初心者や子供と一緒に楽しむ方にもおすすめです。あなたも色を混ぜる楽しさを体感しながら、理想の黄土色を見つけてみましょう。
この記事でわかること:
- 絵の具黄土色を作るための三原色や割合の基本
- アクリル・水彩・ポスターカラーでの黄土色の作り方
- 色鉛筆・クーピーなど異なる画材での黄土色の表現方法
- 黄土色に似た色や100均アイテムを使った代用法
絵の具の黄土色の作り方の基本を理解しよう
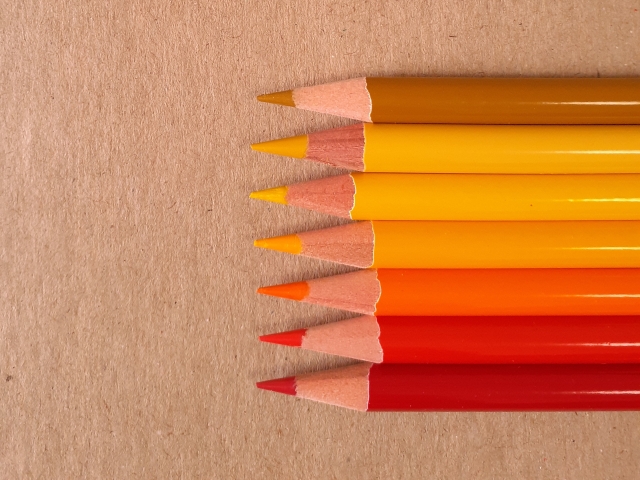
黄土色を自在に使いこなすためには、まずその基本をしっかりと理解しておくことが大切です。
このセクションでは、「黄土色とはどのような色なのか?」という基礎知識から始まり、三原色を使った色の作り方、絵の具を混ぜるときの割合の考え方、便利なシミュレーションアプリの紹介、そして混色表を活用した具体的な作り方まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。
絵の具の黄土色とは?特徴と用途を解説
黄土色(おうどいろ)は、自然の土や砂、枯葉などを思わせる、柔らかく温かみのある中間色です。名前の通り「黄」と「土」を感じさせる色合いで、絵画だけでなく工芸やデザインなど幅広い分野で使われています。
黄土色の特徴は、その落ち着きと自然な風合いにあります。派手すぎず、控えめすぎない絶妙なバランスが魅力で、背景や影、風景の表現に最適です。特に自然物や人物の肌、建物の質感などにリアリティを出したい時に重宝されます。
また、黄土色は「こげ茶色」や「きつね色」と混同されることもありますが、これらよりも明るく黄みがかっているのが特徴です。そのため、他の色と組み合わせる際にも柔軟性が高く、アート作品において幅広い表現を支えてくれる存在です。
使用例としては、秋の風景画や砂浜の表現、土の色、動物の毛色などが挙げられます。特に子供向けの絵画教育でも取り上げられることが多く、初めての混色体験としても取り組みやすい色のひとつです。
黄土色を作るための三原色の使い方
絵の具で黄土色を作る基本は、「三原色」を活用した混色です。三原色とは、赤(マゼンタ)、青(シアン)、黄(イエロー)の3色のこと。この3色をうまく組み合わせることで、さまざまな中間色を自由に作り出すことができます。
黄土色を三原色で表現する場合は、黄をメインに、赤と青をほんの少量ずつ加えるのがポイントです。黄(イエロー)を7割、赤(マゼンタ)を2割、青(シアン)を1割程度の比率からスタートし、少しずつ調整していくのがおすすめです。
注意点として、赤や青を加えすぎると、茶色や灰色に寄ってしまい、黄土色の明るさや黄みが失われます。特に青はごく少量にとどめるのがコツです。色が濃くなりすぎた場合は、白を混ぜてトーンを調整すると自然な黄土色に近づけられます。
また、使う絵の具の種類(アクリル、水彩、ポスターカラーなど)によって発色が異なるので、何度か試し塗りをして理想の黄土色に近づけるのが理想的です。混色はシンプルなようで奥が深く、少しの違いで印象が大きく変わるため、自分なりの「ベストな割合」を見つける楽しさもあります。
絵の具を混ぜる時の基本的な割合とは
黄土色を作る際、理想的な色合いを出すためには、絵の具の混色割合が非常に重要です。基本的な配色の考え方としては、主となる色を多めに、補助的な色を少なめに加えるのがコツです。
具体的には、黄土色の場合は「黄色」を主色とし、「赤」と「青」を補色としてほんの少しずつ加えていきます。例えば、**黄色70%、赤20%、青10%**の割合から始めると、自然な黄土色に近づきやすくなります。
色を混ぜるときは、最初から全量を混ぜるのではなく、少量ずつ試しながら調整していくのがおすすめです。加える色がほんの少し変わるだけで、完成する色味が大きく変化してしまうからです。また、同じ「赤」や「青」でもメーカーや種類によって色のトーンや透明度が異なるため、必ず手持ちの絵の具で一度混色テストをしてから使うのが安心です。
水を加える量でも発色に違いが出るため、特に水彩絵の具の場合は水加減にも注意が必要です。最初は少なめの水で、徐々に調整していきましょう。アクリルやポスターカラーなど不透明な絵の具の場合は、水よりも「白色」を混ぜることでトーン調整するのが一般的です。
混色を安定して再現したい場合は、自分なりの「混色ノート」や「割合メモ」を残しておくのもおすすめです。
黄土色を作るのに便利なアプリやシミュレーションツール
最近では、絵の具の混色をサポートしてくれる便利なアプリやオンラインツールも多く登場しています。特に黄土色のような中間色を作る際には、シミュレーション機能を使うことで理想の色に近づけやすくなります。
代表的なものとしては、**「混色シミュレーター」や「色の辞典アプリ」**などがあります。これらのツールでは、実際に画面上で色を混ぜてみたり、各色の割合を調整したりすることで、完成予定の色を視覚的に確認することができます。
中には「三原色を選ぶだけで自動的に色ができあがる」タイプのアプリもあり、初心者にとっては非常に心強い存在です。特にスマホアプリは、スキマ時間でも気軽に色の組み合わせを試せるので、絵を描く前の準備にも最適です。
また、「混色表」をPDFでダウンロードできるサイトや、子供向けの色合わせゲームアプリなども存在します。これらを活用することで、楽しみながら混色の感覚を身につけることができます。
さらに一部のアプリでは、使っている絵の具ブランドに合わせた色再現が可能なものもあり、実際の手元の画材と近い色を試すことができます。こうしたテクノロジーを活用すれば、黄土色を作る作業がより直感的でスムーズになります。
混色表から学ぶ黄土色の作り方
混色表は、さまざまな色の組み合わせによってどんな色ができるのかを視覚的に確認できる便利なツールです。黄土色のような複雑な中間色を再現する際、混色表を参考にすることで「どの色を、どの程度混ぜればよいか」の感覚をつかむことができます。
多くの混色表では、三原色をはじめとする基本色をベースにして、それぞれの配合バリエーションが一覧で表示されています。黄土色を探す場合は、黄色を中心に赤や青を加えたエリアに注目してみましょう。そこに表示された色味が、自分の求める黄土色に近ければ、その比率を参考にすればよいのです。
混色表の良い点は、一目で比較ができるため、失敗を避けやすくなることです。また、トーンの違いも記載されているものが多いため、より明るい黄土色にしたいのか、それとも落ち着いた深みのある色にしたいのか、といった調整のヒントにもなります。
最近ではPDFでダウンロードできる混色表や、ウェブ上で操作できるデジタル混色表もあり、自分の持っている絵の具に合わせてカスタマイズすることも可能です。特に初心者にとっては、実際の混色前に「完成形の予測」ができるため、絵の具の無駄を減らすというメリットもあります。
絵の具別に見る黄土色の作り方のコツ

黄土色の作り方は、使用する絵の具の種類によって微妙に異なります。このセクションでは、アクリル絵の具や水彩絵の具、ポスターカラーといったそれぞれの特性に合わせた混色のポイントをご紹介します。
また、色鉛筆やクーピーで黄土色を表現する工夫や、ダイソー・セリア・キャンドゥなど100均で手に入る絵の具の活用法、さらに黄土色に似たこげ茶色やきつね色との違いについても詳しく解説していきます。
アクリル絵の具で作る黄土色のポイント
アクリル絵の具は発色が良く、乾燥後の耐久性も高いため、プロから趣味のユーザーまで広く使われています。そんなアクリル絵の具で黄土色を作る際には、いくつかのポイントを押さえておくことで、より理想の色味に近づけることができます。
まず基本となるのは、黄色(イエローオーカーなど)をベースに、赤(バーントシェンナやカドミウムレッド)と青(ウルトラマリンなど)をごく少量ずつ加える方法です。アクリル絵の具は隠ぺい力が高いため、わずかな色の追加でも大きく色味が変化するので、混ぜる際は少しずつ慎重に進めましょう。
アクリルならではの特徴として、「乾くと少し暗くなる」点も考慮する必要があります。混色時には理想より少し明るめに仕上げておくことで、乾燥後にちょうどよい黄土色になることが多いです。また、ツヤ出しメディウムやマットメディウムなどを加えることで、表面の質感を調整することも可能です。
黄土色を作る際は、ホワイトを加えて明るさを調整することも有効です。純粋な黄色・赤・青だけではどうしても深みが強く出てしまうため、白でトーンを抑えることで優しい印象の黄土色に仕上がります。
アクリル絵の具は速乾性が高いため、パレット上での作業時間が短くなりがちです。あらかじめ色の構成や混色割合をシミュレーションしておくと、慌てずに理想の色を作ることができます。
水彩・ポスターカラーでの黄土色の出し方
水彩絵の具やポスターカラーを使って黄土色を表現する際には、それぞれの絵の具の特性に合わせた工夫が必要です。特に水彩絵の具は透明度が高く、重ね塗りや水の量で大きく発色が変わるため、混色の感覚にも違いがあります。
水彩絵の具で黄土色を作る場合は、黄色(レモンイエローやイエローオーカー)をメインに、赤(バーントシェンナなど)を少しずつ加えていきます。そこに、ほんの少量の青(ウルトラマリンなど)を加えることで深みが生まれます。水の加減が肝心で、濃く出すと茶色寄りに、薄くのばすと砂浜のような淡い色味になります。パレット上で試し塗りをしながら微調整するのが成功の鍵です。
一方、ポスターカラーは水彩よりも不透明で発色が鮮やかです。こちらでも黄土色を出す際は黄色を多めに、赤・青を少しずつ加えて調整しますが、ポスターカラーは重ね塗りで下の色が隠れてしまうため、一発で理想の色に近づける必要があります。
いずれの絵の具でも、白を混ぜることで柔らかい黄土色に、黒を加えるとくすんだ落ち着いた印象に変化します。明るさや濃さを意識して、用途に合わせた調整をすることが大切です。
色鉛筆やクーピーでの黄土色の言い換えと表現法
色鉛筆やクーピーで黄土色を表現する場合、絵の具とは異なり混色が難しいため、「色の言い換え」や「重ね塗り」を活用することがポイントになります。黄土色に相当する色がセットに含まれていない場合は、代用可能な色をうまく組み合わせて使いましょう。
代表的な言い換え表現としては、「きつね色」「キャメル」「サンド」「ライトブラウン」「オーカー」などがあります。これらの色は製品やメーカーによって若干の違いはあるものの、黄土色のニュアンスに近いため、置き換えとして十分機能します。
また、実際の塗り方としては、黄色をベースに塗った上から、赤茶系の色を軽く重ねることで、自分だけの黄土色を作ることが可能です。重ねる順番や筆圧の調整によって、色味にグラデーションをつけることもでき、深みのある仕上がりになります。
特にクーピーは柔らかく重ね塗りがしやすい画材なので、表現の幅が広がります。子供向けの画材セットには「土色」や「ベージュ」といった名称で近い色が用意されていることもあり、そうした色を探してみるのも良いでしょう。
色鉛筆やクーピーの特性を理解し、組み合わせや言い換えを駆使することで、絵の具を使わなくてもナチュラルで味わいのある黄土色を表現できます。
100均(ダイソー・セリア・キャンドゥ)で揃う絵の具の活用術
絵の具といえば専門店で買うイメージがありますが、近年では100均でも高品質な絵の具が手に入るようになっています。特にダイソー、セリア、キャンドゥといった人気ショップでは、アクリル絵の具や水彩絵の具の種類も豊富で、初心者が試すには十分なクオリティを備えています。
黄土色のような中間色は単色では販売されていないことも多いため、複数の基本色を組み合わせて作る必要があります。例えば、ダイソーのアクリル絵の具では「イエロー」「レッド」「ブルー」といった三原色が揃っており、これを使って黄土色を作ることが可能です。絵の具の濃さや粘度はやや個体差があるため、試し塗りを重ねて調整すると良いでしょう。
セリアでは小容量の絵の具がセットで販売されていることが多く、ちょっとした工作や子供の自由研究にもぴったりです。色の種類が限定されていることもあるため、混色を前提とした使い方がおすすめです。
キャンドゥはアクリル系のカラー展開がユニークで、オーカー系の色味やベージュなど、黄土色に近い色が見つかる場合もあります。また、筆やパレット、混色用の紙皿などの周辺グッズも手に入るので、絵の具初心者でも手軽に環境を整えることができます。
100均の画材は価格が手頃なぶん、実験的に色を試すハードルが低く、特に子供や初心者にとっては色づくりの第一歩として最適です。使いこなせば、プロ顔負けの色表現も夢ではありません。
こげ茶色・きつね色など黄土色に似た色との違い
黄土色とよく似た色として、「こげ茶色」「きつね色」「ベージュ」「キャメル」などが挙げられますが、それぞれには明確な違いがあります。これらを正しく理解することで、目的に応じた色選びや表現の幅が広がります。
こげ茶色は、黄土色よりも赤みが強く、暗くて深みのある印象を持つ色です。木材や影の表現によく使われ、力強さや重厚感を出すのに向いています。一方の黄土色は、もっと明るく黄みが強いため、より軽やかで自然な印象を与えます。
きつね色は、名前のとおり焼いたパンや揚げ物の色としても親しまれている色で、黄土色と非常に近い色合いです。違いを挙げるとすれば、きつね色の方がやや赤みを含んでおり、温かみが強いのが特徴です。黄土色の方がナチュラルで落ち着いた印象になります。
また、キャメルやベージュは、ファッション分野などでも使われる色名ですが、これらは黄土色よりもさらに淡く、グレーや白に近いトーンを持っています。絵画で使うには物足りないと感じる場面もあるかもしれませんが、背景やグラデーションとして使うと効果的です。
こうした微妙な違いを理解することで、「伝えたい印象」や「描きたい対象」に応じて最適な色を選べるようになります。黄土色は中間色としてのバランスが良く、さまざまな近似色と組み合わせても調和しやすい便利な色です。
まとめ

この記事のポイントをまとめます。
- 黄土色は自然や落ち着いた表現に適した土系の色合い
- 三原色(赤・青・黄)を使えば自分で黄土色を作ることが可能
- 絵の具を混ぜる際は、黄色をベースに紫や赤青を少量ずつ加えるのが基本
- 色を作る際には「割合」を意識することが仕上がりの鍵になる
- アプリやシミュレーションツールを活用すれば色の確認がしやすい
- 混色表を参考にすることで配色バリエーションの幅が広がる
- アクリル絵の具では発色が強いため、慎重な混色が必要
- 水彩やポスターカラーでは水分量の調整が重要なポイント
- 色鉛筆やクーピーでは、他の茶系色と組み合わせることで黄土色を表現できる
- ダイソー・セリア・キャンドゥなど100均の絵の具でも黄土色は再現可能
黄土色は「土の色」「砂浜の色」「自然の温かみ」を感じさせる魅力的な色です。決まったレシピがあるわけではなく、混ぜる色の割合や使う絵の具の種類によって仕上がりが変わるため、自分なりのベストなバランスを見つけることが重要です。
三原色を使って自作したり、100均や既存の色を活用したりと、さまざまな方法で黄土色にチャレンジしてみてください。自分だけの理想的な黄土色を見つける楽しさを、ぜひ体験してみましょう。