「明日」という言葉を読むとき、ふと「あすとあした、どっちが正しいの?」と迷った経験はありませんか?
実は、どちらも正しい読み方であり、使用する場面やニュアンスによって自然と使い分けられているのです。しかし、読み方はどちらも正しくとも意味としては使う場面によって違いがあります。
本記事では、「明日」は「あす」と「あした」のどっちが正しいのか、読み方の違いや意味、使い分けの理由を深掘りし、ビジネスや日常生活における最適な表現を解説していきます。さらに、NHKや文語表現「みょうにち」、言い換えの工夫まで幅広く取り上げ、日本語の奥深さに迫ります。
この記事でわかること
- 「明日(あす・あした)」の違いと正しい使い方
- ビジネスやフォーマルな場面で適した読み方とは
- NHKで採用される読み方の理由
- シーンに応じた「明日」の言い換え表現の工夫
「明日」は「あす」と「あした」のどっち?意味の違いや読み方

「明日」という漢字には、複数の読み方が存在しますが、実際にどのように使い分ければよいのか迷う人は少なくありません。ここでは、「あす」と「あした」の違いや使い方の背景について、語源や意味、使用される場面をもとに詳しく解説していきます。
「明日」の正しい読み方とは?
「明日」という漢字には、「あす」と「あした」という2通りの読み方があります。どちらも間違いではなく、文脈や話し手の意図によって使い分けられています。
実際のところ、「あす」と「あした」は発音こそ似ていますが、微妙に異なる印象を与えることがあります。たとえば、ニュースやアナウンスなどのフォーマルな場面では「明日(あす)」と読むのが一般的です。一方で、家族や友人との会話など、日常的なカジュアルな文脈では「明日(あした)」の方が自然に使われる傾向があります。
また、辞書や文法書でも「明日」は訓読みで「あした」「あす」「みょうにち」と複数の読み方が掲載されています。特に学校教育やメディアにおいては、子どもたちにはまず「あした」という読み方を教えられることが多く、それが定着している背景もあります。
このように、「明日」は一つの漢字でも複数の読み方を持ち、どれが正しいというよりも、「どんな場面で、どの読み方がふさわしいか」が重要なのです。
「あす」と「あした」の意味の違い
「あす」と「あした」は、いずれも「今の次の日」を表す言葉です。つまり、時間的な意味では違いはほとんどありません。ですが、使われる場面や語感には違いが見られます。
まず「あす」は、やや硬めの響きがあり、ニュース、ビジネス文書、公式発表などで多用されます。短く、口調が締まるため、読みやすく聞き取りやすいという利点があります。そのため、NHKなどのニュース放送でも「あす」が標準的に使われていることが多いです。
一方で「あした」は、親しみやすく、やわらかい響きが特徴です。話し言葉としての使用頻度が高く、特に家庭内や友人同士の会話ではこちらの方が一般的です。また、童謡や詩などの文学的な表現にも「あした」はよく登場します。たとえば「明日も元気にがんばろうね」のような文では、「あす」よりも「あした」の方が自然で感情が伝わりやすいです。
つまり、「あす」と「あした」は意味の上では同じでも、「どんな印象を与えたいか」「誰に向けて話すか」によって、選ぶべき言葉が変わるのです。
NHKでは「あす」「あした」どっちを使っている?
NHK(日本放送協会)では、ニュースや気象情報、番組内の案内において、「あす」の読み方が原則として採用されています。これは、NHKが「ことばの統一性」と「聞き取りやすさ」を重視しているためです。
実際に、NHKの「ことばのハンドブック」などの運用基準を確認すると、「明日」は原則「あす」と読み、「あした」は使用を避ける傾向があることが明記されています。「あす」は発音が短く明瞭で、放送に適しているとされているのです。
このような基準は、全国に向けて情報を発信する公共放送として、誰にでも伝わる明瞭な言葉を使うための工夫です。そのため、NHKのニュースを見て育った人たちにとっては、「明日=あす」という印象が強く残っているかもしれません。
一方で、ドラマやバラエティ番組などでは、出演者の自然な言葉遣いとして「あした」が使われることもあります。したがって、NHKでも番組のジャンルや内容によって使い分けられているのが実情です。
ビジネスシーンで好まれるのは「あす」?
ビジネスの現場では、「明日」は「あす」と読むのがより適切とされることが多いです。なぜなら、「あす」は語感が引き締まり、文章としても話し言葉としてもフォーマルな印象を与えるためです。
たとえば、ビジネスメールや社内通知、会議資料などで「明日」と書く場合、「あした」と読むとややくだけた印象になります。それに対して「あす」と読むと、内容が引き締まり、より公式な文書としての信頼感が生まれます。
実際に、「あすご対応いただけますでしょうか」「あすの会議に向けて準備をお願いします」といった表現は、社内外のコミュニケーションでよく使われています。
ただし、口頭での会話の際には、相手との関係性や職場の文化によって「あした」が使われることもあります。特に親しい同僚同士の会話や、比較的フランクな職場環境では、そこまで気にされないケースもあるでしょう。
とはいえ、初対面の相手や、上司・取引先に対して話すときには、「あす」を選んだ方が無難です。ビジネスにおける「敬意」と「丁寧さ」を示す表現として、「あす」の方が一歩リードしていると言えるでしょう。
会話では「あした」、文章では「あす」が多い理由
日常会話の中では、「明日」を「あした」と読む人が圧倒的に多いです。一方、文章や放送・ビジネス文書の中では「あす」と読むのが一般的です。この違いには、言葉のもつ印象の違いと、文体との相性が関係しています。
まず、「あした」は柔らかく親しみやすい響きを持っています。そのため、友人や家族との何気ない会話で自然に使われることが多く、心の距離を近づける効果もあります。「あした遊ぼう」「あしたどうする?」といった表現は、感情が伝わりやすく、日常会話に溶け込みやすいのです。
一方で、「あす」は言葉が短く引き締まって聞こえるため、ニュース原稿や報告書などの硬い文章に適しています。語尾が「ス」で終わるため、文全体が締まって聞こえるというメリットもあります。また、文章中に「あす」が登場すると、全体のトーンをフォーマルに整えることができます。
このように、「あした」は話し言葉としてのやわらかさ、「あす」は書き言葉としての格式という、自然な使い分けが日常的に行われているのです。
「明日」は「あす」と「あした」のどっちか使い分けや言い換え
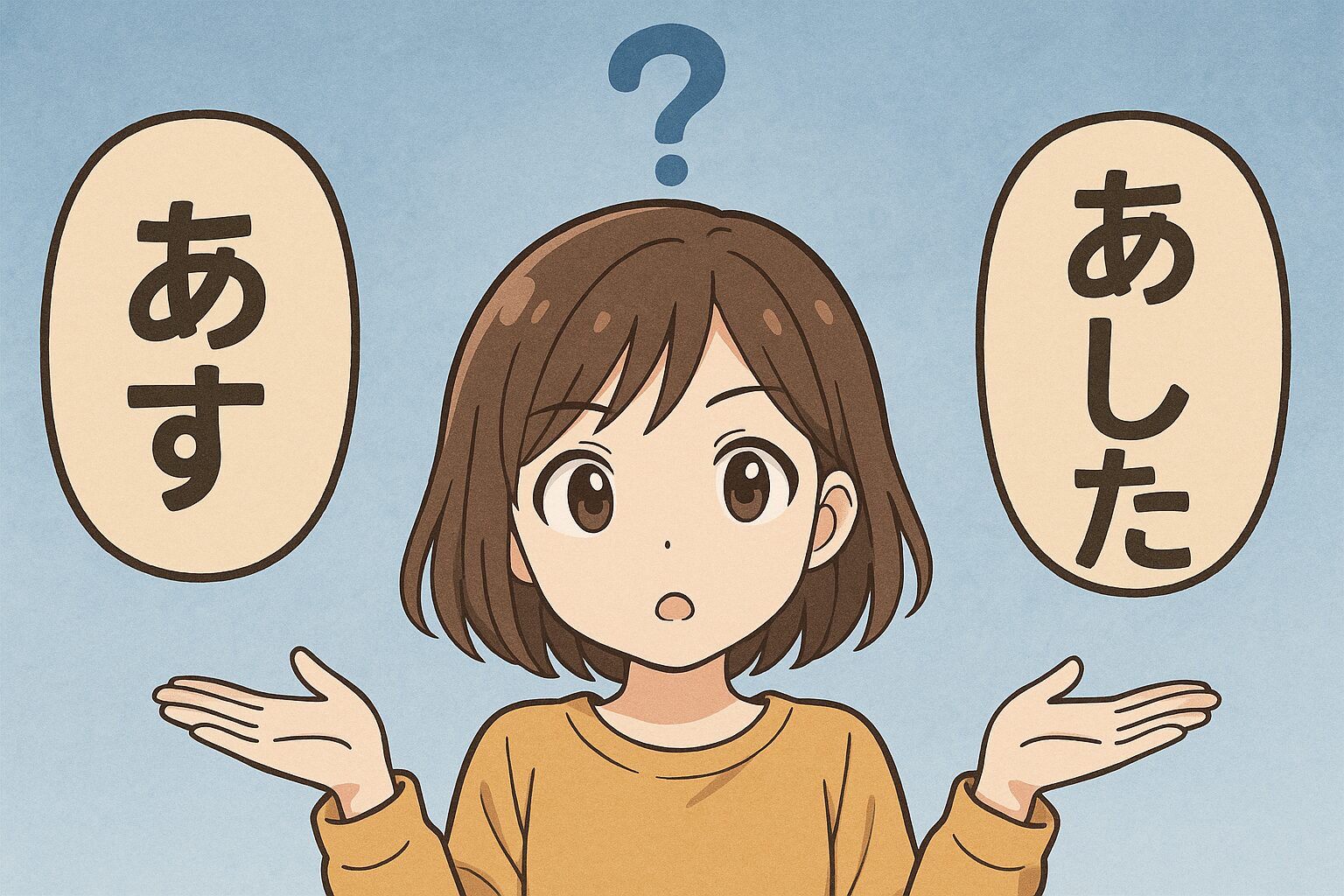
「明日」という言葉は便利な一方で、使う場面によっては誤解を招いたり、表現が曖昧になったりすることもあります。ここでは、「明日」を使わずに表現する工夫や、「みょうにち」との違い、そしてシーンに応じた適切な言い換え表現について紹介します。読み手や聞き手にとって、より伝わりやすい言葉を選ぶヒントになるはずです。
「明日」を使わない言い回しの工夫
場面によっては、「明日」「あす」「あした」という言葉自体を使わずに、別の表現で伝えた方が適切なこともあります。これは、曖昧さを避けたり、聞き手への配慮を示したりするための工夫です。
たとえばビジネスメールでは、「明日」は相手によって解釈がずれる可能性があるため、「○月○日(曜日)」のように具体的な日付で伝えることが推奨されます。「明日中に対応をお願いします」よりも、「9月13日(金)中に対応をお願いします」とした方が、誤解の余地がなくなります。
また、家庭や学校などで「明日」という表現が曖昧になりそうな場合は、「次の日」「翌日」といった言い換えも有効です。特に読み物や物語の中では、「翌朝」「その翌日」などを使うことで、時間の流れを自然に表現できます。
他にも、丁寧な表現を心がけたいときは、「後日」「近日中に」「近日改めて」などの言い回しを使うこともあります。これらの表現は、相手にプレッシャーを与えずに伝えるテクニックとして重宝されます。
このように、「明日」をあえて避けることで、より明確で丁寧な印象を与えることができるのです。
「あす」「あした」と「みょうにち」の違いとは?
「明日」には「あす」「あした」だけでなく、もう一つの読み方として「みょうにち」もあります。いずれも「翌日」を意味する言葉ですが、それぞれに異なる使い方とニュアンスがあります。
「みょうにち」は、特に古風で文語的な表現として使われることが多いです。たとえば、文芸作品、詩、歴史的文章などでは、「みょうにち」は荘厳で落ち着いた響きをもたらします。また、仏教用語としても使われることがあり、儀式や法話の中で「明日は(みょうにち)は〜」と用いられるケースもあります。
一方、「あす」や「あした」は現代的で口語的な表現です。「あす」はフォーマルなシーン、「あした」はカジュアルなシーンで使い分けられることが多いのに対し、「みょうにち」は現代の日常会話ではあまり登場しません。
また、意味の上では3つとも「今の次の日」を指しますが、「みょうにち」はやや抽象的で、具体的な日付を示す際には不向きです。そのため、実務的な用途や明確な日時の指示には「あす」「あした」の方が好まれます。
つまり、「みょうにち」は歴史的・文学的背景を感じさせる言葉であり、現代語としての使用は限定的。場面や目的に応じて、うまく使い分ける必要があります。
シーンに応じた適切な言い換え表現
「明日」「あす」「あした」は便利な言葉ですが、繰り返し使うと文章が単調になったり、意味があいまいになることもあります。そうした場合には、シーンに応じた適切な言い換え表現を活用することで、文章の印象をグッと洗練させることができます。
たとえば、ビジネスシーンでは「翌営業日」「次回打ち合わせ日」「○月○日」など、より具体的で明確な表現が好まれます。「明日提出してください」ではなく、「9月13日(金)中にご提出ください」と伝えることで、誤解を避けることができます。
また、日常会話やメールなどでは、「次の日」「その翌日」「後日」などの表現も使いやすいです。たとえば「明日は忙しいかも」と言う代わりに、「その翌日は予定が入ってるかも」と言い換えることで、少し丁寧な印象を与えることができます。
さらに、文学的・詩的な表現を意識する場合、「来る朝」「やがて来る日」などの言い回しも可能です。これらは物語やエッセイなどで使うと、情感を込めた表現になります。
このように、シーンに応じて「明日」という言葉をさまざまに言い換えることで、文章や会話の質を高めることができるのです。
「あす」「あした」の使い分けに迷う理由
多くの人が「明日」を読むときに「あす」と読むべきか、「あした」と読むべきか迷うことがあります。これは、両方が正しい読み方であることと、明確なルールが存在しないことが原因です。
学校では「あした」という読み方を先に習うことが多いため、自然と日常会話でもそれを使うようになります。しかし、ニュースやビジネスの世界では「あす」が一般的に使われており、社会に出てから「あす」という読み方の存在感に気づく人も少なくありません。
さらに、国語辞典や新聞社・テレビ局ごとの言語方針も異なるため、何が「正解」なのかはっきりしないのです。たとえば、ある新聞では「あす」、別の雑誌では「あした」と使われていることもあります。このようなバラつきが、読者や視聴者に混乱を招く一因となっています。
また、SNSやメールなどのカジュアルな文体が広まったことで、「あした」が主流になっている場面も多く、「あす」と使うとやや硬すぎる印象を与えることもあります。
このように、「あす」「あした」のどちらを選ぶかは、自分が置かれた状況・相手・媒体・目的によって柔軟に判断する必要があるのです。
「明日」という漢字の成り立ちと読み方の歴史
「明日(あす・あした・みょうにち)」という漢字は、日常的によく使われるにも関わらず、その成り立ちや読み方の歴史は意外と知られていません。
まず、「明日」の漢字を分解すると、「明」は“あかるい”、“次の日”のニュアンスを含み、「日」は“太陽”や“日付”を意味します。この2文字が組み合わさることで、「明るい日=現在の次の日」という意味が生まれました。
では、なぜ複数の読み方が存在するのでしょうか。それは、日本語における「和語」と「漢語」の読み方の混在が影響しています。
- 「あした」→ 和語(日本固有の言葉)
- 「あす」→ 和語(短縮された形)
- 「みょうにち」→ 漢語(中国由来の読み)
このように、同じ表記でも由来の異なる言葉が重なっているため、時代や場面に応じて複数の読みが共存してきたのです。
たとえば、平安時代の和歌では「あした」が頻繁に使われており、文学作品の中でも親しまれていました。その一方で、律令制度などに関わる官僚文書では「みょうにち」のような漢語表現が好まれていた背景があります。
つまり、「明日」という漢字は、日本語の歴史そのものを映し出すような存在であり、その読み方の多様性こそが、豊かな言語文化を物語っているといっていいでしょう。
まとめ
今回は、「明日」は「あす」と「あした」のどっちが正しいのか、読み方の違いや意味、使い分けの理由を深掘りし、ビジネスや日常生活における最適な表現を解説してきました。
この記事のポイントをまとめます。
- 「明日」は「あす」も「あした」も正しい読み方である
- 「あす」はフォーマル・公式な場面でよく使われる
- 「あした」は親しみやすく、日常会話でよく使われる
- NHKでは明瞭さを重視し、「あす」が標準読み
- ビジネスでは「明日=あす」と読むのが一般的
- 会話では柔らかさを重視して「あした」が自然
- 「明日」を使わない言い換えも工夫のひとつ
- 「みょうにち」は文語的で文学や儀式に使われる
- 表現を明確にし誤解を防ぐには「○月○日」などが有効
- 「あす」「あした」の迷いは使い分けの柔軟性にある
「明日」の読み方ひとつをとっても、日本語の奥深さが感じられます。「あす」か「あした」かに正解はなく、場面や相手、目的に応じた使い分けが大切です。
ビジネスやメディアでは「聞き取りやすさ」や「格式」が求められる一方、日常会話では「親しみやすさ」や「自然さ」が重視されます。言葉は使う人の思いや工夫が反映されるものです。
ぜひ状況に応じて最適な表現を選び、日本語の魅力を日々のコミュニケーションに活かしてみてください。


